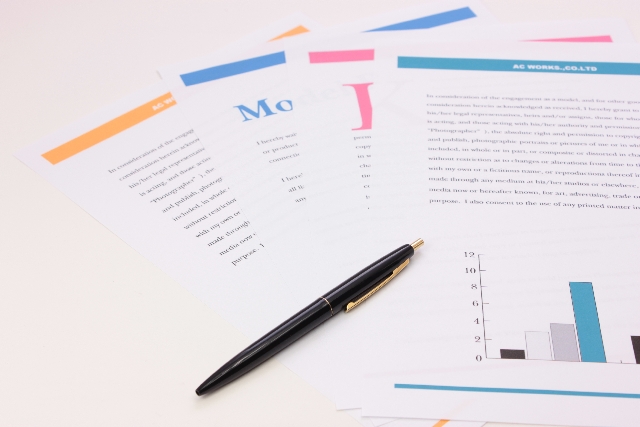


退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)
元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。
そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?
私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。
この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)
元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。
そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?
私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。
この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。
と、いうのが一般的だと思います。
>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。
これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
と、いうのが一般的だと思います。
>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。
これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
失業保険受給についておしえてください。失業手当てをもらうのですが、いくつか聞きたいです。今現在旦那の扶養にはいってます。基本日当?は4600円で90日です。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1、旦那の扶養はいつから抜けたらいいのですか?(保険証を返す時期)
2、扶養から抜けなかったらどうなるのですか?
3、90日で、満額で414000円になります。それでも扶養を抜ける必要ありますか?
4、扶養に抜けたら、失業手当てをもらったあと、すぐにまた旦那の扶養に入ることは可能ですか?
いっぱい質問ばっかりでごめんなさい。お願いします。
1.基本手当の支給対象期間の初日です。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。
2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。
3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。
被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。
4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
受給期間延長を解除してもらう、ということなら、手続きしたその日付で資格喪失でしょうね。
2.後日判明した場合、さかのぼって資格取り消しです。
当然、さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
また、再度手続きするまで“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)ではありませんから、さかのぼって取り消された日以降に受診した医療費は健保に返還することになります。
3.基本手当は日額で表現するものです。1日ごとに、その日の分の支給・不支給が決定され、支給されるものですから。
※現実に毎日認定するのは面倒だから28日分まとめるだけ。
被扶養者・第3号被保険者の判定では、日額・月額を年額に換算して判定します。
日額3612円=130万円以上、ということです。
4.一般的には、すぐに認定されますが、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらに聞いて下さい。
失業保険と扶養について。無知のため知恵をお貸しください。
平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。
失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?
また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?
よろしくお願いします。
平成24年2月で退職し、旦那の扶養に入るつもりでいました。
ですが、失業保険をもらうとその間扶養に入れず、自分で国民保険、国民年金に入らなくてはいけないと知りました。
失業保険をもらって国民保険、国民年金に加入するのと失業保険をもらわず、扶養に入るのとではどちらが得なんでしょうか?
また、扶養に入るのに1、2月分のお給料と退職金の額は関係ありますか?
よろしくお願いします。
扶養にはいる・・・・ご主人の健康保険(健保組合・健康保険(協会けんぽ管掌))にはいることですね。
保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。
入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)
国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。
国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。
ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)
(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。
注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。
正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)
国民年金について
国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。
どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。
もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
保険に入る要件は、加入時点から1年向こうの奥さんの収入額が一定額以内(130万円が目安)にあること(当然、主たる生計維持者が夫であること)です。・・・・各健保組合やご主人の会社の保険担当者に確認してください。
入れないことは、1月2月の収入と失業保険の額が超えるのではないでしょうか?(額が不明ではっきりはわかりませんが)
また、制度上、加入できないかもしれませんね。(私にはわかりません)
国民健康保険税(料)について
介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)が含まれる
世帯は、介護保険料分も併せて納めて頂くことになります。
納税義務者は世帯主となります。
また、国民健康保険税は国民健康保険に加入している方の分を
すべて合算し、納税義務者である世帯主に賦課されます。
国民健康保険税は、次の(1)から(4)までの合算額、
年度ごとに賦課されます。 また、40歳以上65歳未満の方は、
介護保険料分も合算されて賦課されます。
ただし、以下の税率は市町村で違ってきます(ここが重要)
(1)所得割額・・・前年の課税対象所得に、それぞれの数字をかけた額
(2)資産割額・・・土地・建物に係る固定資産税額に、それぞれの数字を
かけた額。
(3)均等割額・・・加入者1人あたりの額。
(4)平等割額・・・1世帯あたりの額。
注.その他賦課限度額や、世帯の前年合計所得が軽減基準額を
下回るときは、(3)均等割額と(4)平等割額の一部が軽減されて賦課されます。(市町村で違います)
4.退職所得については、国民健康保険税の算定対象になりません。(退職所得はないものとみなされます。)
5.年度途中で国保に加入された場合は月割りにて算定されます。
正確な計算は、一度お住まいの役所にお問い合わせください。試算してくれます。(前年の収入がわかるもが必要)
国民年金について
国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は15,020円(平成23年度)です。
どちらが得かは、すべての項目を試算してもらって比較する
しかありませんね。
各役所や会社の担当者に試算していただいてみてください。
この場では、あたなの前年の年収や失業保険料、給付期間、
固定資産関係、家族構成(その収入など)、
旦那さんの情報(扶養手当額も影響しますよ)、
特に、お住まいの国保税(料)率など多くの情報が全くありませんので、
判断は不可能です。
もし揃っていても、素人が計算するより専門家にお願いしましょう。<(_ _)>
関連する情報